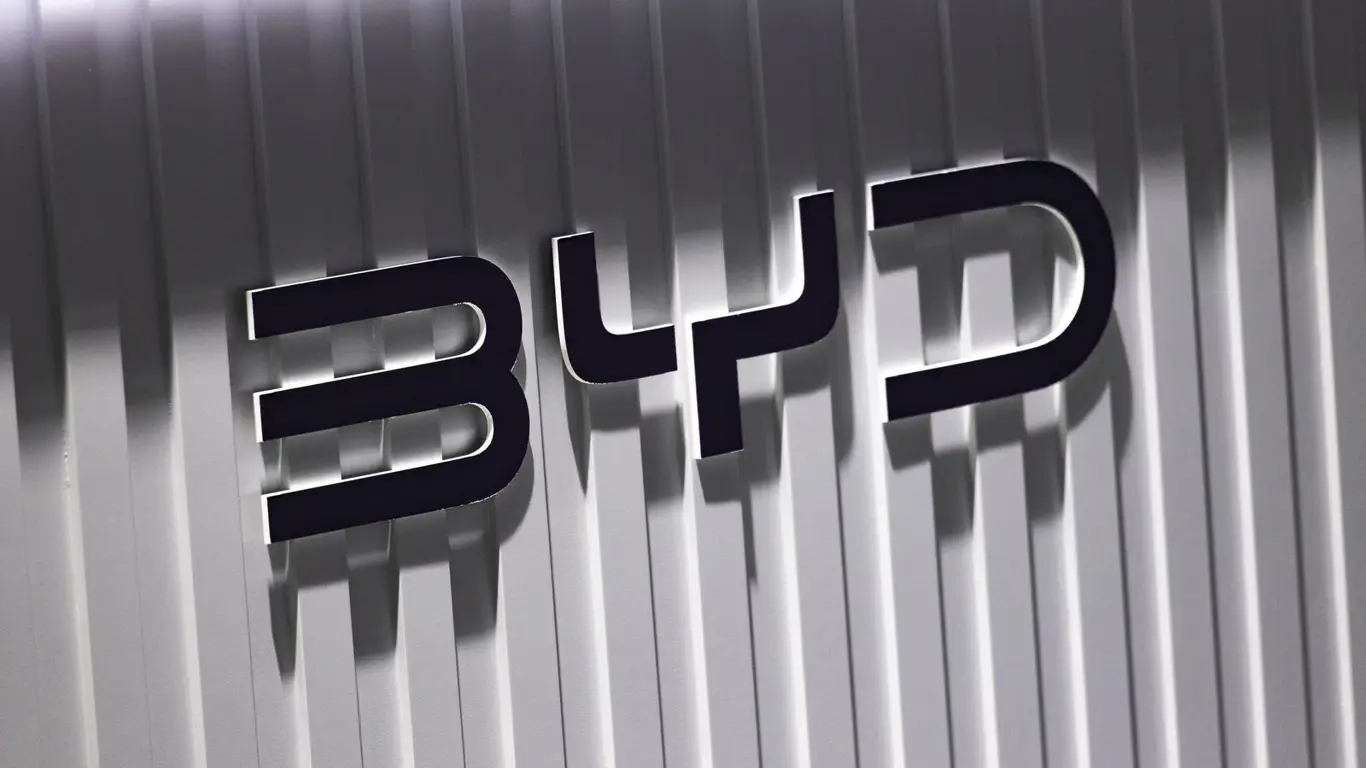https://tarantas.news/ja/posts/id2302-bydhao-zhou-gaancapxing-ping-jia-nofu-za-hua-niku-yan-an-quan-xing-hadian-shu-yoriwen-mo-tosu-eru-zui-xin-purotokorutonogiyatsupuzhi-zhai
BYD豪州がANCAP星評価の複雑化に苦言、安全性は点数より文脈と訴える—最新プロトコルとのギャップ指摘
BYDオーストラリアが指摘するANCAP星評価の難しさと安全性の文脈
BYD豪州がANCAP星評価の複雑化に苦言、安全性は点数より文脈と訴える—最新プロトコルとのギャップ指摘
BYDオーストラリアのスティーブン・コリンズ氏が、ANCAPの星評価制度の複雑化と年次差を問題視。5つ星と4つ星のギャップ、最新プロトコルとの関係、購入者への伝わり方を解説。三菱の見解やSealion 8のeCall対応、コナやスイフトとの比較も含め、星の数だけでは測れない安全性の文脈と選び方を分かりやすく伝えます。
2025-11-16T13:59:34+03:00
2025-11-16T13:59:34+03:00
2025-11-16T13:59:34+03:00
BYDオーストラリアは、ANCAPの星評価制度があまりに複雑になり、一般の購入者には年式や試験手法の違いによる評価の差が見分けにくくなっていると指摘している。ブランド責任者のスティーブン・コリンズ氏は、3年ごとの更新サイクルと膨らみ続ける評価項目が、安全スコアをほとんど迷路のようなものにしてしまったと述べた。評価の年次差を読み解くのは、クルマ好きでも容易ではないだろう。ANCAPはすでに、評価の有効期限を6年とする取り組みで分かりやすさを狙っているが、受け止められ方の問題は依然として残る。一方で、現行のBYD各モデルは当時の基準でいずれも5つ星を獲得しているのに対し、ヒュンダイ・コナからスズキ・スイフトまで、多くの競合はいまや4つ星あるいは3つ星にとどまる。プロトコルの更新がカタログより速いペースで進む状況では、文脈のない「星の数」だけが並ぶとメッセージがぶれやすい。星の並びをポスターで比べても、実像は伝わりにくいというわけだ。コリンズ氏は、Sealion 8のような新型でもeCallを必須装備とするなど、同社は安全面で可能な限りの上積みを目指していると強調。それでも、顧客の要望により適した仕様が結果的に4つ星になるなら、その状態で投入する用意があるともしている。得点に最適化した仕様より、使い手に合うセットアップを選ぶ判断は現実的だ。三菱も似た考えで、5つ星の獲得を追い続けることはコスト増につながり、常に正当化できるとは限らないとみている。最新のプロトコルでは、古い5つ星車より安全性で上回る4つ星車もありうるが、そのニュアンスを購入者に伝えるのは難題だ。結局のところ、評価は点数と同じくらい文脈が重要で、買い手にとっては星そのものと同様に「わかりやすさ」が価値になる——そのことを思い出させる話だ。
BYDオーストラリア, ANCAP, 安全評価, 星評価, 5つ星, 4つ星, プロトコル, eCall, Sealion 8, 三菱, ヒュンダイ・コナ, スズキ・スイフト, 自動車安全, 評価の有効期限, 6年, オーストラリア市場
2025
news
BYDオーストラリアが指摘するANCAP星評価の難しさと安全性の文脈
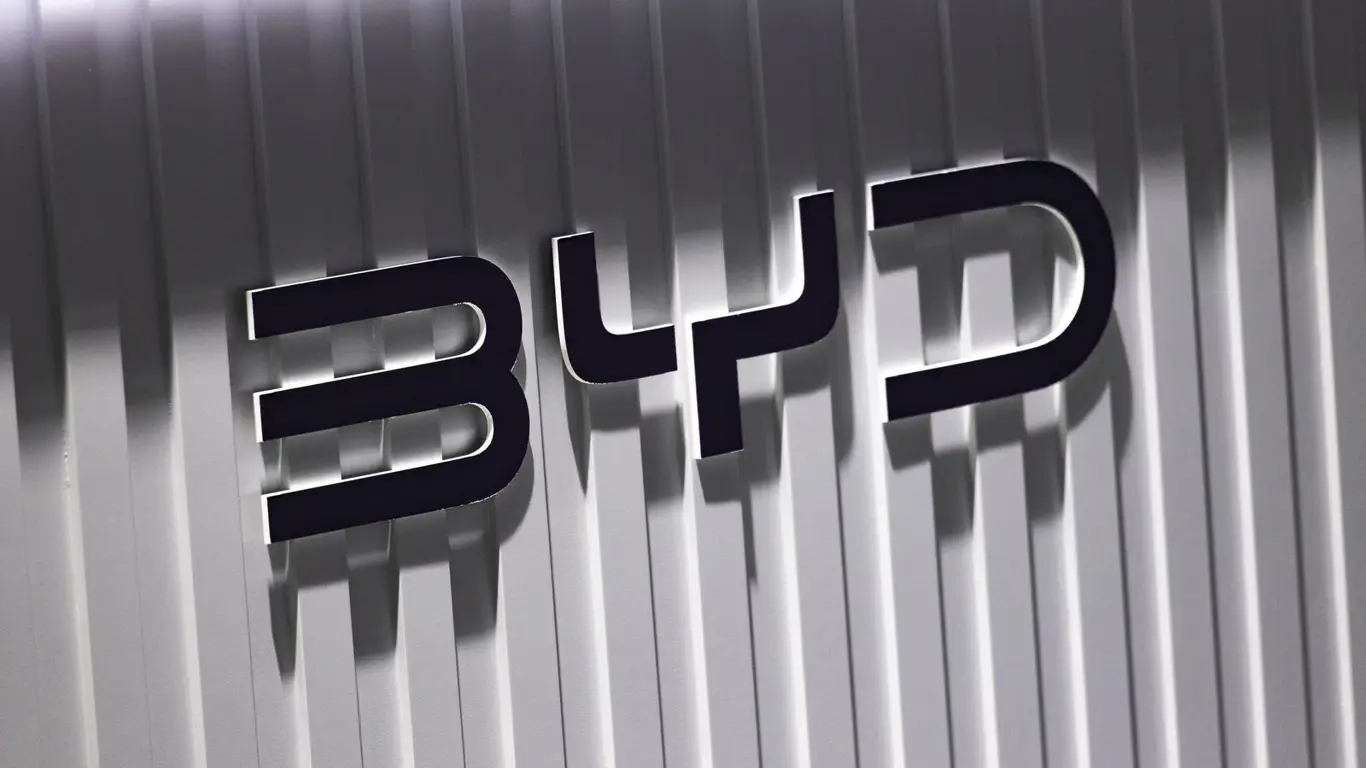 A. Krivonosov
A. Krivonosov

David Carter, Editor
13:59 16-11-2025
BYDオーストラリアのスティーブン・コリンズ氏が、ANCAPの星評価制度の複雑化と年次差を問題視。5つ星と4つ星のギャップ、最新プロトコルとの関係、購入者への伝わり方を解説。三菱の見解やSealion 8のeCall対応、コナやスイフトとの比較も含め、星の数だけでは測れない安全性の文脈と選び方を分かりやすく伝えます。
BYDオーストラリアは、ANCAPの星評価制度があまりに複雑になり、一般の購入者には年式や試験手法の違いによる評価の差が見分けにくくなっていると指摘している。ブランド責任者のスティーブン・コリンズ氏は、3年ごとの更新サイクルと膨らみ続ける評価項目が、安全スコアをほとんど迷路のようなものにしてしまったと述べた。評価の年次差を読み解くのは、クルマ好きでも容易ではないだろう。
ANCAPはすでに、評価の有効期限を6年とする取り組みで分かりやすさを狙っているが、受け止められ方の問題は依然として残る。一方で、現行のBYD各モデルは当時の基準でいずれも5つ星を獲得しているのに対し、ヒュンダイ・コナからスズキ・スイフトまで、多くの競合はいまや4つ星あるいは3つ星にとどまる。プロトコルの更新がカタログより速いペースで進む状況では、文脈のない「星の数」だけが並ぶとメッセージがぶれやすい。星の並びをポスターで比べても、実像は伝わりにくいというわけだ。
コリンズ氏は、Sealion 8のような新型でもeCallを必須装備とするなど、同社は安全面で可能な限りの上積みを目指していると強調。それでも、顧客の要望により適した仕様が結果的に4つ星になるなら、その状態で投入する用意があるともしている。得点に最適化した仕様より、使い手に合うセットアップを選ぶ判断は現実的だ。
三菱も似た考えで、5つ星の獲得を追い続けることはコスト増につながり、常に正当化できるとは限らないとみている。最新のプロトコルでは、古い5つ星車より安全性で上回る4つ星車もありうるが、そのニュアンスを購入者に伝えるのは難題だ。結局のところ、評価は点数と同じくらい文脈が重要で、買い手にとっては星そのものと同様に「わかりやすさ」が価値になる——そのことを思い出させる話だ。